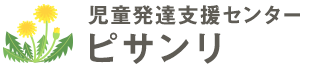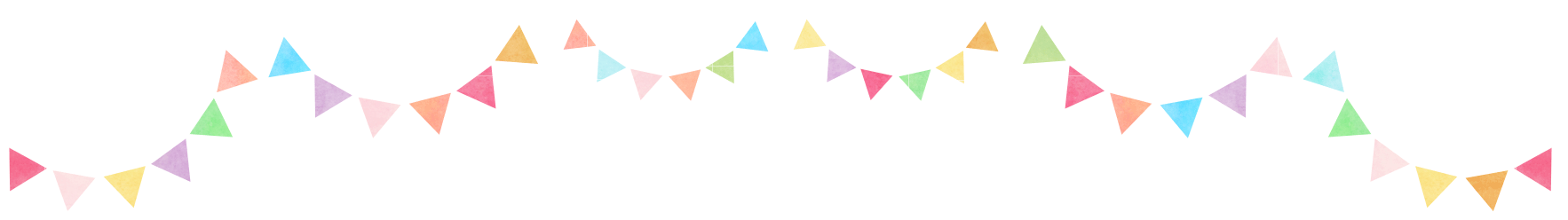

支援プログラム
- ■法人(事業所)理念
- 児童発達支援センターピサンリは、自閉スペクトラム症をはじめ、心身の発達に心配のある子どもを対象として療育・支援を行う施設です。保健、医療、福祉、教育の関係機関と連携を取りながら、一人一人子どもの早期発見と早期からの支援を重視します。幼児期の子どもと家族の支援を目的とします。
- ■支援方針
- 幼児期に、TEACCHプログラムのアイディアの一部を取り入れて、見て分かりやすい・取り組みやすい情報提供やレイアウトをすることで、「わかる」「できる」体験を沢山積み重ね、社会で自分らしく生活していくための自尊心を高める支援を行います。また、将来社会で共に生活していくために、穏やかな人間関係を築き適切なやりとりを積み重ねることで、コミュニケーション力を高める支援を行うことを方針とします。
- ■営業時間
- 8:30~17:30
- ■送迎実施の有無
- あり
支援内容
| 本人支援 | 健康・生活 |
|
|---|---|---|
| 運動・感覚 |
|
|
| 認知・行動 |
|
|
| 言語・コミュニケーション |
|
|
| 人間関係 社会性 |
|
|
| 家族支援 |
|
|
| 移行支援 |
|
|
| 地域支援・地域連携 |
|
|
| 職員の質の向上 |
|
|
| 主な行事等 |
|
|